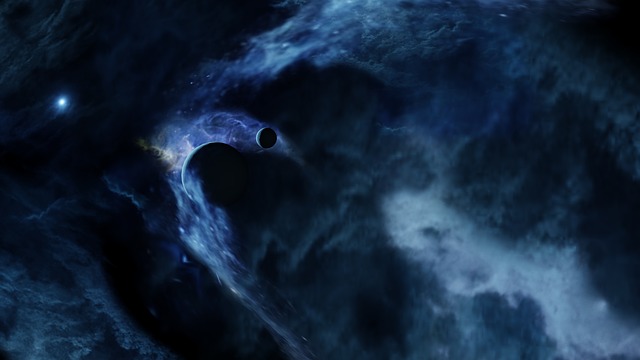
カッシーニのミッション終了に触発されて、まだ宇宙熱が冷めやらず色々調べてしまいました。
三連休は宇宙づくしですね。
関連記事:さよならカッシーニ。土星の環の中で。
外宇宙探査
正確には外宇宙ではなく、外太陽系と呼ばれる火星よりも外側の領域のことなのですが、外宇宙という響きがロマンチックなのでこう呼びます。
正直な話、火星までの領域は物理的に人類(人がという訳ではなく人が作り出した機械も含む)が到達してしまっているので、なんかロマンというよりは現実的な話に聞こえてしまうので、どちらかというと外宇宙の方が興味あります。
2004年に火星に着陸したNASAの探査機オポチュニティはもう10年以上も火星の大地で活動していますので、まるでGoogleアースでも見るかのように、火星の様子がみれます。
外部サイト:Curiosity Rover Report: Four Years on Mars – NASA
月面探査なんかはもう、最近中国も参戦して各国の資源獲得競争になっているように思いますので、夢がないですね。
天王星・海王星の探査
カッシーニが突入した土星の次に外側にあるのは天王星と海王星。
太陽系の中では若干地味めなこれらの惑星の探査は、今から30年近く前にボイジャー2号が最接近したのを最後に探査機は到達していません。
学生の頃教科書でみた、のっぺりとした薄緑色の天王星と、気持ち悪いくらい真っ青な海王星の写真から、まだ変わっていないということです。
土星の輪の中まで到達したのだから、次はこれらの惑星のレポートも、もっとみてみたいですね。
海王星の方はネプチューン・オービターと呼ばれるNASAの惑星探査プロジェクトの案が10年前に出ていたのですが、資金繰りなどで延期になっているようです。
元々は、2016年に打ち上げて8-12年で海王星に到達する計画だったようなので、理論上は可能ということでしょう。
生きているうちに到達するのを願いたいところです。
冥王星の探査
冥王星は、2006年に惑星から準惑星に格下げになったことで一時話題になりました。
しかし、意外にも探査は天王星や海王星よりも進んでいて、冥王星探査を目的としたNASAの惑星探査機、ニュー・ホライズンズが2015年に最接近を果たしています。
30年前の教科書には、冥王星だけ謎という感じでちっちゃな白丸のような写真だけ載っていてはがゆい思いをしていたものですが、今はこんなに鮮明な写真がみられるようになりました。
天王星や海王星は、木星型のガス惑星であることがわかっていて、地面がないのでどんなに頑張っても着陸することはできません。
海王星なんて、風速が時速2,000kmあるそうです。
なので、調べてもそんなに意味ないかなーなんて考えられているのかもしれませんね。
冥王星の外側にはエッジワース・カイパーベルトと呼ばれる、太陽系を同心円状にとりまく小惑星群が控えており、冥王星はその代表格ではないか、と考えられています。
今までは、『太陽系のもっとも外側にいる、小さな謎の惑星』という、どちらかというと陰のイメージだった冥王星ですが、現在は『太陽系の外縁部の小惑星群を代表する天体』という陽のイメージに変わってきています。
また、カロンと呼ばれる弟のような天体を従えていることから、2重天体ではないかという説もあるようです。
恒星間探査
1970年代に打ち上げられ、太陽系の外縁部を調査したボイジャー1号と2号は、今や太陽系を脱出して星間空間に出ました。
現在は何もない恒星間に飛んでくる微弱な放射線や星間物質を観測した結果を地球に送りながら、あてもない旅を続けるという、孤独なミッションを行なっています。
太陽から遠ざかるに連れて太陽電池の出力も弱まり、地球に送られてくる信号もこれからどんどん弱くなっていくでしょう。
太陽系からもっとも近いお隣の恒星系には、今のスピードで最短距離をまっすぐ進んだとしても約8万年はかかると言われていますので、もはやロマンの領域に入ったと言えるでしょう。
これらには有名な人類のメッセージが積載されていますので、さながら大海に流された小ビンのように、外宇宙の隣人に届く日を待ちわびるという、夢のある話になりました。
まとめ
人類は太陽系の隅まで光を当てつづけて、だいぶその中のことがわかってきました。
また20年30年後には、きっともう一つ外側の宇宙まで光が当たっているんだろうなと考えるとワクワクしますね。

