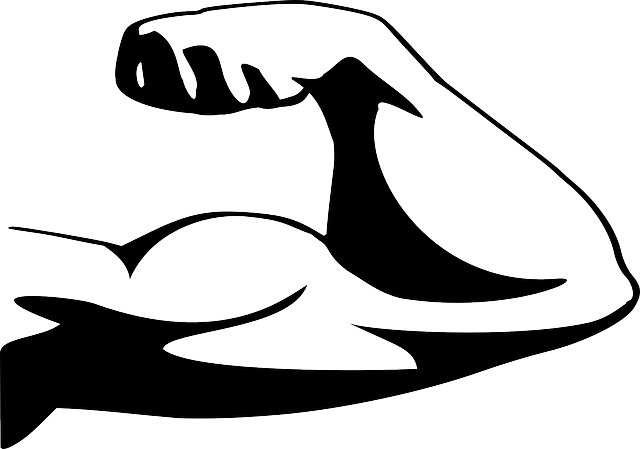
名著「嫌われる勇気」を読んでいる。
この本は、フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」と称される、アルフレッド・アドラーの思想を「青年と哲人の対話形式」で物語風にまとめた取っつきやすい本だ。
その中で、印象的な表現があったので紹介したい。
この世でもっとも強い者
哲人:アドラーはいいます。「わたしたちの文化のなかで、誰がいちばん強いか自問すれば、赤ん坊であるというのが論理的な答えだろう。赤ん坊は支配するが、支配されることはない」と。赤ん坊は、その弱さによって大人たちを支配している。そして、弱さゆえに誰からも支配されないのです。
子供がいる生活をはじめてから、うっすらと感じていたことを明確に言葉で示されてはっとした。
そうだ。妻が子供をみごもってからというもの、わたしたち夫婦の生活はすべて子供の支配下におかれたのだ。
わたしたち夫婦だけではない。
道行く人すべて、おさな子を抱えた夫婦をみるやいなや多くの人が道をあける。
電車の優先席は、最下層だった若い夫婦時代から一転、最優先に変わる。
飛行機の優先搭乗も、3歳未満のお子さまは最高ランクマイラーよりも上だ。
それはひとえに、圧倒的な肉体的・精神的弱さは、わたしたちの文化においては最大限庇護しなければならない対象とうつるからだ。
そして、赤ん坊がもつ無限の可能性も、それを失った大人たちにはまばゆく見える。
実はみんな気づいている
この事実は、自然にすべての人が気づいていることで、これを無意識に利用する大人がいる。
上記の引用文は「引きこもりはなぜうまれるのか?」についての青年と哲人の議論の中で発された言葉だった。
アドラーの思想は、人間の行動はすべて「目的」にねざしており、過去のできごとは関係ない、という「目的論」の考え方をとる。
「ものごとには原因がある」という原因論に立脚すると、引きこもりは何らかの過去のつらい経験・トラウマがもとで発生するもの、ということになるが、哲人はこれを否定する。
アドラーの思想によると、引きこもりは「外に出たくないから、あえて弱い自分を作り出している」というのだ。
あえて「弱さ」という鎧をまとうことで、親や周囲との関係の中で「特別な存在」であろうとする。
近年、犯罪をおかしたものに「精神的な疾患が見受けられ、裁判所が責任能力が問えるかどうか審議中」という報道が多いが、これもこの思考を無意識に使っているということもあるのではないだろうか。
人生は転げ落ちる石のよう
哲人と青年の議論は「どうして幸福に生きられないのか」という青年の悩みから始まった。
人間の強さは、世の中の赤ん坊のすべてがもっている「肉体的精神的にもっとも弱い」という特徴と「可能性は無限大」という特徴の2つをあわせた最大の状態からスタートして、年をとるごとに減っていく。
赤ん坊も何年かたち、さらに弱い妹や弟ができると、「もうおにいさんなんだから」の合言葉を皮切りに徐々に弱さを失っていく。
小学校・中学校・高校と進み、スポーツや勉強、その他色々な活動で徐々にまわりと比べられるようになって、できることとできないことが明確になり、可能性も失っていく。
ここで重要なのは、「失う」ことは誰にでも当たり前のことであり、問題ではないということだ。
問題なのは、「失うことを認められないこと」だと哲人は語る。
失うことを認められない人は、幸福に近づけない。
すなわち、この事実を受け入れられず失った弱さを取り戻そうとする行為や可能性を失うまいとあえて行動しない行為を行うことが、不幸を招くということだ。
逆にこの事実を受け入れ、別のやり方でこの下り坂にあがらう行為が人々を幸福へと導くというのだ。
この別のやり方がなんなのかはもう少し読み進めてから考えてみようと思う。

